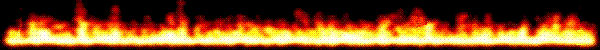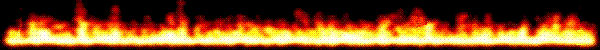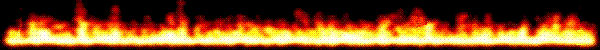
 『炎で書いた物語』最終章8
『炎で書いた物語』最終章8
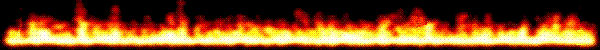
<戦士(さむらい)達は今>(その20)
1986年四月、ぼくたち一家は日本に帰ってきた。
とりあえず京都の実家に着いて、東京で仕事ができる住居を探しに出た。
色々不動産会社を廻って音の出せるスペースの確保は都内では難しいと感じ
た。
埼玉県の大袋と東川口に二年契約の借家があるというのでその二軒に絞った。
埼玉県なら東京に近くて住み良さそうだった。
数年の間に仕事の目鼻をつけて移転したり、アメリカへ帰ったりできるかと考
えた。
まず、大袋に行ってみるとかなり大きい家だった。
大きい音を出せるスペースがあった。
各部屋を回って、なかなかいいと思った。
ところがある和室に入るとなんだかぞくっとした。
なにか得体の知れない不気味さを感じて、
妻も同じように感じるというので早々に退散した。
次に東川口に回ると大きさは大袋の家より小さかったが新築だった。
各部屋にまだ電灯もついていないし人の住んだ形跡がなかった。
なぜ家を新築して住みもしないで借家にしてしまったのか不思議だったが
近所の人の話でわけが見えてきた。
この家を建てた人は外国の駐在員で日本に帰ってきて
今度は腰を落ちつけようと思ってこの家を建てることにした。
ところがやっと建てて引っ越し荷物を運び込んでいる最中に
会社から転勤命令が届いたという。
自分の建てた家に一日も住むことなく次の勤務地に出発することになった。
その勤務地はサンフランシスコだった。後は不動産管理会社にまかせて
とるものもとりあえず任地に出発してしまった。
まるで元々ぼくたち一家を迎えるために見も知らぬその人が
この家を新築してくれたようだった。
ぼくたちはサンフランシスコに行ったことから一度日本に帰ってみるか、
という気になったのだがなにか妙な符合だった。
そして数回目の契約更新時、この家の持ち主の現住所を見て驚いた。
なんとそこにはぼくが仕事していたロスアンジェルスの地区の通りの名前が書
かれていた。
これはただの偶然なのだろうか。
まるで、見えない大きな手が登場人物を人形、あるいは将棋の駒のようにひょ
いと運んで
居場所を入れ替えただけのように感じた。
五十二億もいる人間の中から入れ替える者を選ぶだけでもすごい。
そんなことをするにはぼくなどの量り知れない意味があったのだろう。
はじめはあまり気に留めなかったがこの家の番地は九十七番地の十である。
あるころからそれが意味のある数字のように思えだした。
それは九十七年の十月を意味するのではないかと。
新築の家も、すでに築十年を過ぎ、
その番地の示す年月がもう目の前に迫ってきた。
******************************************************
<究極的かごめ唄考補遺、うしろの正面のだれか探し>
以前、『究極的かごめ唄考』と題してかごめ唄について
あれこれ考えたがもう、ククリの年も九月に入ったので
唄の最後で問われ続ける 『うしろの正面』のだれかも
顔を覗かせそうな気がする。
うしろの正面だあれ、と問われるとなぜかうすうす感じる
シュール・リアリスティックな思いがある。
自分のうしろの正面には自分自身がいるのではないかと
何とはなしに思ってしまう。
それは最初の人類として生まれた頃の記憶のせいだろうか。
地球上にポツンとひとり生まれたアダムはなにもない球上の世界で
かれの視界をさえぎるものはなにもなく、地球を一周した光に反射する
自分の姿しか見えなかったことだろう。
たったひとりの世界では振り向けば後ろには自分自身がいるだけだった。
アダムが自己増殖できる存在、アンドロギュノスであったとき、
かれの中心、おなかに神は宿っていた。
やがてアンドロギュノスの身体を二つに分けたときに
神の居場所の印がヘソとして残った。
二つに分けられた身体を前後でみると大切な部分はほとんど前部に集められ
た。
人体をミクロコスモスとしてとらえると左目が太陽であり、
右目が月として前面に向かって光を放っている。
われわれは光の反射によってしかものが見えないので
前面にあるものしか認識できない。
われわれにとっては前面だけが光の世界なのである。
それに反して人の『後ろ』である背面には光を放つものがない。
ということは背面は人にとって光の射さない暗闇の世界なのである。
それゆえ、人は背後を畏れ何度も振り返る。
目の光を闇に照射して浮かび上がるものを見ようとするのだ。
後ろの正面のだれかを探すことは暗闇の住人を特定することにほかならない。
お腹と書いて『おなか』と読むのは
中ということばが神の居場所を指しているからである。
腹(はら)は高天原の原(はら)と通じる。
それは身体の上下左右前後の中心で臍下丹田と呼ばれる位置である。
そのおなか(高天原)に集われていた神々があるとき、
隠退されて背の側に移ってしまわれた。
それが天の岩戸伝説である。
そのことを示すのが前面のおなかに対する背中ということばなのだ。
光の射さない暗闇の世界である背に中をつけて背中と呼ぶのも、
そこに神々がおられるからである。
『背』とは北の月、北とは基田で基の神の居場所。
人の畏れる背中の闇には元の神々が集われている。
天の岩戸は人の背で閉ざされたのである。
その岩戸を背戸と呼ぶ。
エジプトではオシリスを殺したイシスの弟Seth(セト)
日本では出雲に封印をかけたアマテラスの弟、狭門(セト)として知られる。
それは人の背の戸のことなのだ。
以前、『一二三四五六七八九十』を
『人フタ見よ、いつ無に為すやここの戸を』と解いたとき、
ここの戸』の示す戸がどこの戸か特定できなくて曖昧なままだった。
『うしろの正面』に焦点を当てて考えた現時点で
ついにそれが『背の戸』であることが露(あらわ)になった。
それはそこから向こうを見えない闇と捉えて
畏怖するわれわれの心を閉ざす戸である。
天の岩戸閉め以来、この世の実権を奪ったセトが構築した
人の前面の光の世界が
実は日仮(ヒカリ)の世であることが今暴かれようとしている。
背中の暗闇に隠退されていた真の光が射す時が迫った。
うしろの正面だあれ、の答えは隠退されていた基なる神であった。
***********************************************************
<SOUND小劇場>『風の中の北京家鴨(ダック)』
あの日、おいらは黄河のそばの沼のほとりのあひるだった。
支那大陸の奥地で生まれたばかりの豊かな風が
柳の葉を靡(なび)かせる春の昼下がり、
かあさん家鴨のあとをヨチヨチ、クワッククワックついて歩いた。
家族仲良くみんなで水の上、スイスイ、クワッククワック並んで泳いでた。
そんなのどかな記憶も突然とぎれてしまった。
ある日、羽のない大きな獣が現れておいらたちを捕まえてしまったんだ。
それが人間を見た最初だったよ。
オンボロ馬車にゆられゆられて着いたところは花の都、北京の市場。
どじょう髭の肥ったおじさんがズラリ並んだ土の壷に
おいらたちを一羽ずつ差し込んで言った。
「わたし、ワンさん、オマエラ運良かった。これから楽できるよ。
毎日、食べて寝て大きくなるだけ」
おいらはやっと顔だけ出してあたりを見回した。
みんなも背伸びしながら覗いてた。
道行く人が慌ただしく行き過ぎて土煙で目が見えなくなったよ。
おなかが空いてガアガアと喚(わめ)きだしたとき、
くちばしになにかを詰め込まれ、目を白黒して呑み込んだ。
情けないけど、それがおいらたちの食事のしかただったんだ。
「オマエラ、もっと静かにしたほうがいいよ。暴れるとスジ張るからダメ」
ワンさんはこわい目をして餌を配ってた。
一番うるさかった仲間は二三日餌をもらえなかった。
それからあまり騒がなくなっちゃった。
それでも、一度大笑いしたことがあるよ。
かわいい女の子がおかあさんを振り返って言ったんだ。
「ねえ、おかあさーん、ほらここにきれいなお花が並べてあるわ」
おいらたちがいっせいにその子に顔を向けたら
キャッと叫んで逃げてった。
そういえば離れて見れば花みたいに見えるのかと
みんなで笑いながら自分が植物なのか動物なのかわからなくなった。
あんまり笑いすぎたもので涙が出てきて
泣いてるのか笑ってるのかもわからなくなったよ。
そんなある日、見たこともない白い鳥が市場の空を横切った。
おいらはとても羨ましくて、オーイと呼びかけた。
その鳥はニッコリ微笑んで降りてきた。
「わたしの名前は帝(テイ)、こんなところでなにしてるの。どうして飛ばな
いの」
「おいらの名は労苦(ルーク)。だっておいら壷の中。足も萎えたし羽も萎え
た。
たとえ壷から出られてもやっと歩けて泳ぐことしか能のないあひる。
飛ぶなんて、とてもとても」
初めて見るその美しい鳥に見とれながら答えたんだ。
でもなぜかなんだかなつかしい気がしたよ。どこかで会ったことがあるみたい
な。
「あら、わたしには壷なんか見えないわ。
自分で自分を縛ってないで、その翼を羽ばたいてごらんなさいな。
きっとあの大空へ舞い上がれるわ」
白い鳥はそう言って翼を大きく広げて夕陽に向かって飛んでった。
そのとき、おいらの心に勇気みたいものが湧いてくるのを感じた。
それから真剣に空を飛ぼうと思った。あの鳥といっしょに飛びたいと。
毎日毎日、壷の中で動かない翼を懸命にうち振ってみた。
疲れはてて眠ると、あの鳥が夢の中で囁いた。
「あひる、飛びなさい、ルーク、飛びなさい。あの大空に帰るのよ。
あの大空はあなたのふるさとよ。いつもあなたを待ってるの。
遠い昔に忘れた翼の業(わざ)を思い出すのよ」
「でも、どうしてもだめなんだ。どうか自由にしてください。
おいらはただ泣き濡れているだけのあわれなあひるなんだ」
泣き言を言っても届くわけがなかった。
でもテイのことを思うだけで甘いような切ないような気持ちがして
安心して深い眠りに落ちていった。
「このごろ、おまえおかしいよ、壷の中でバタバタするのイケナイ。
かたくなって売れなくなる」
ワンさんはハラペコなおいらの前を素通りしてエサを配り終えた。
「好々(ハオハオ)、 おまえよく肥えてきた。えらいえらい。
この壷の中、カラダいっぱいになった。
ここの暮らしはもう卒業よ。おめでとう。明日いいとこ連れていく。
みんなも見習うといい」
おいらの一番仲の良かった仲間にワンさんはニコニコ笑いかけたんだ。
そのころにはもうおいらたちもうすうす気づいていた。
ハオハオの行き先が飯店であることを。そこでなにが起こるかも。
不意に胸が詰まって涙があふれだした。
でももう泣いてなんていられなかった。
見回すとみんなもなんとかしてハオハオを助けたいと
思っていることが伝わってきた。
その時だった。涙の向こうに幻みたいにあの美しい翼がうるんで見えたのは。
ぐんぐん、あの白い鳥は近づいてきた。
おいらの心臓はドキドキ高鳴った。
「さあ、飛ぶのよ。労苦(ルーク)飛ぶのよ」
おいらは羽を激しく震わせた。
それでも壷はまるで動かない。
やっぱり無駄かと力尽きたとき、
雲の影から黒い大きい鳥の姿が現れた。
それは大鷲だった。白い鳥を狙ってつけてきたんだ。
嘴(くちばし)と足の爪が凶器のように光ってた。
おいらはおもわず叫んだ。
「テイーッ、危ない。鷲だ」
テイはなぜか気づかない。
おいらはおどり上がって必死でもがいた。
バタンと壷が倒れて割れたとたん、空中に舞い上がってた。
大鷲は白い鳥に鋭い爪を開いてつかみかかろうとしている。
おいらは全力で体当たりした。
するとどうしたことか大鷲は空中に掻き消えてしまった。
おいらはまるで肩すかしを食った力士みたいに雲の中につっこんだ。
「うふふふ、とうとう飛べたわね。とうとうね。うふふふ」
テイは笑い声を残して大きく羽ばたいた。
翼をひるがえしひと振りするごとに青空に吸い込まれていった。
「そうだ、おいらは今飛んでるんだ」
風の中においらはいた。
生まれて初めて翼を飛ぶために使っている。
空の深さに、大地の広さにおどろいた。
「おーい、みんなもおいでよ」
われにかえって呼ぶと
次々に壷が倒れて仲間たちがころげでた。
ワンさんは右往左往して捕まえようとした。
でもその手をすり抜けて、みんなは飛び立った。
あの鳥の向かった方向にみんなで追いかけてゆこうとしたとき、
青空のどこかから声がした。
「わたしの役目は終わったの。これからはあなたがたの番よ」
こうして、おいらは風の中を泳ぐあひるになった。
どこかで姿を見かけたら呼んでおくれよ。
見えない壷に囚われたあなたが忘れた力を甦らせて
ともにこの大空を翔ぶ日のために。
(おわり)