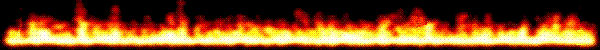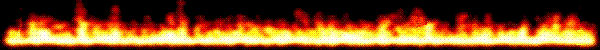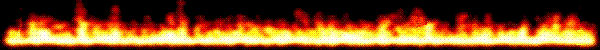
 『炎で書いた物語』最終章8
『炎で書いた物語』最終章8
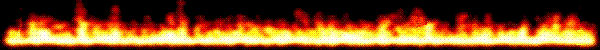
<戦士(さむらい)達は今>(その17)
京都の父が肺炎で足早に逝った。七十四才だった。
前兆はなかった。
数年前に心臓を患ってペースメーカーをつけはしたが
それなりに健康を回復していた。
六月七日(土)の朝に月初めの挨拶の電話をかけたとき、
父が出ていつもと変わらぬ口調で言った。
「今、お母ちゃん、ゲートボールに行っとおる、帰ってきたら電話さすわ」
父は電話で話すのが苦手であまり自分では話をしようとせず
いつも母と話させようとした。
「いや、ええよ、一時頃にまたかけるから」
「そやな一時やったらきっと帰っとおるわ」
それが父とぼくのこの世での最後の会話になった。
それから三日後の六月十日(火)
父が肺炎で朝六時から徳州会病院へ入院したという電話が母からあった。
母は取り乱していて様子がよくわからなかった。
数日前にに父の普段通りの声を聞いたところなので不思議だった。
そして、その一週間後、六月十七日(火)3:29 PM
「お父ちゃん今死んだ」と母から電話。
正式な永眠の時刻は午後三時十分。
母は過労で声が出なくなっていた。
詳しいことは聞けなかった。
ぼくは長男で埼玉在住だが次男である弟はパリに住んでいる。
急いで帰ってきても葬式に出席できない。
パリに電話すると留守電になっていたので、一応メッセージを入れておいた。
翌朝、ぼくたち一家は通夜と葬式出席のために京都へ出発した。
新幹線で京都について乗り換える、
近鉄奈良線のホームの大神神社の看板がやけに大きく目に付いた。
実家に着くと湯潅を済ませてきれいに死化粧してもらった父の遺体が柩に納められてい
た。
湯潅は水を先に入れて後で湯を入れた逆さの湯で生前の汚れを
洗い浄めるという。
十八日(水)七時から八時まで通夜、
十九日(木)午前十一時から十二時まで告別式。
火葬のあとで初七日の法事も執り行われた。
最近は世の中が忙しくなって親戚が何度も集まりにくくなったので
初七日もその日に済ませてしまうという。
ぼくは自分が何宗に属しているのか把握してなかったが
親戚の話によると浄土真宗の仏光寺派だそうだった。
親戚は導師として経を詠む僧侶の詠み方が西本願寺式で節が違うので
合わせて詠みにくいと言っていた。
ぼくはそんなものかと思いながら配られた経の本を開いてみんなと声を合わせて
歌うように詠んだ。難しい文字が多くて考えているとおいてけぼりになる。
驚いたことにみんなの唱和する声で身体の細胞が震えるのを感じた。
仏教の音霊のバイブレーションにじかに触れてこれはすごいと感心した。
難しい漢字の羅列は意味不明のようで
死者にも生者にも多大な影響を与えることを確信した。
父は、生前よく、死ぬときは苦しまないでコロッと死にたいと言っていた。
入院一週間で逝ったのだからその言葉が半ば達成されたとぼくは感じた。
親戚の方が
「死んだら何もないのやろなあ」と言っていたので、
「死んだら無や、何もないのや。何もなくなるのや」
と父が三年前の正月に何度も言っていたのを思い出した。
ぼくは、そんなことはないと反論したが聞き入れてくれなかった。
一般にそう思っている人は多いようだが
実際に死ぬまでわからない人にはわからないので仕方ない。
何もなくなってしまった者に対してどうして人々は経を詠むのか。
遺影に向かって苦笑しながら
「どや、お父ちゃん、何もないか?」
と問うた。
答えはなかったが、父も苦笑したことだろう。
いつかまた、どこかで会えることもあるだろう。
*************************************
SOUND小劇場『赤鬼譚』
>> 94/06/04 解かれた封印から赤い色を頼りに、隔り世から鬼が来る…
三年続きの凶作が六蔵を駆り立てた。
富裕な農家を容赦なく襲った。
返り血を浴びて逃げ帰る六蔵の姿は赤鬼そのものだった。
近郊の村々では自警団を組織した。
六蔵は動物的な勘で警戒の網をすり抜けて荒し回った。
ある日、押し入った家の倉には一粒の米もなかった。
六蔵は荒れ狂い、剣を振り回した。
その目の前に痩せ細った子供たちが恐れる風もなくばらばらと現れた。
「おじちゃん、なんか食うものくれ、この倉の壁はあんまり美味(うも)うなかった」
「おまえら、おれが怖くないのか、。そばにいると死ぬぞ」
「どうせ、わいらもすぐ死ぬんじゃ、壁土ばかりでは腹がくだるばっかりじゃから」
一番年かさらしい男の子があばら骨の浮き出た薄い胸を掻きながら言った。
「親はどうした」
「流行病(はやりやまい)で死んでしもうた」
昔の自分に出会ったような気がして六蔵は力が抜けた。
その時、家の外に集まってきた自警団の声がした。
「倉の中に鬼がおるぞ」
六蔵は慌てて倉を飛び出した。
行く手は棒切れや農具を手にした男たちにふさがれている。
逃げ道はない。
大声をあげてその真っただ中に飛び込んだ。
だれかが鍬で六蔵の足を払った。
かれはもんどりうって地面に額から激突した。
それっとばかりに袋叩きにあって気を失った。
*******************************************
さっきから同じ光景がくり返される。
六蔵のふりかざした剣の下で脅える庄屋の与平とその妻、貞。
「六さん、わたしを連れて逃げてよ。
この与平なんぞ初めから好きでもなんでもなかった。
金で買われたようなものだよ。こんな時代に生まれたばかりに
あんたと添えなかった」
「なにを、このアマ、妾でも良いからとわしに泣きついてきたくせに、
六蔵、わしはおまえの代わりにお貞一家を救ってやったのだ」
貞は六蔵と将来を誓った仲だった。
六蔵は貞と婚礼を挙げる費用を貯めようと出稼ぎに村を出たのだ。
しかし、飢饉はどこも同じだった。
とうとう、自分の口を糊(のり)することもできなくなった。
遂に、野盗にまで身を落とした。
櫛こうがいの類も貞のためにと奪ったりした。
なにをしても貞のことが頭から離れなかった。
疚(やま)しさは感じても時代のせいにして生き延びてきた。
ある程度、蓄えができて、村に帰ってきたとき、
貞はすでに家にはいなかった。
庄屋の与平に嫁いだと聞いて号泣した。
与平には妻子がいるはずだった。
怒りが噴き上げた。
与平の家まで韋駄天走りに走った。
飛び込んだ六蔵の目の前で二人は哀願とけなし合いを始めた。
ええい、黙れ、だまれ…。
命乞いする二人に六蔵は容赦なく剣を振り下ろした。
血しぶきがあがる。
そのたびに場面が戻って与平と貞の哀願とけなし合いが始まる。
うんざりするほど同じ場面がくり返す。
*********************************
「六、六、六」
だれかが遠くで呼んでいる。返事をしてすぐに参上しなければ…。
急がなければ叱られる、只今参ります…。
はっと目を開くと僧侶の顔があった。
「六よ、目が覚めたか。赤鬼というのはおまえのことじゃったか。
なるほど、こいつめ鬼の顔になりおった。わしを憶えておるか。
この破れ寺の主、法海じゃ、一口水でも飲め」
幼い頃、口減らしのためにしばらく預けられていた寺の住職だ。
身体が縛られて身動きできない六蔵は水差しの水にむせた。
「村人の裁きはついたそうな、明朝、首切りらしい。
村人が交代でのこぎりで引くそうじゃ。
おまえのようなろくでなしのためにご苦労なことじゃて。
あのお貞まで手に掛けたそうじゃな。一緒になるのかと思うておったが…」
縄がきつくて息もしづらい。
「六、わしがおまえの引導役として一晩預かることになったのじゃが
死ぬ前にひとつ良いことをして死なぬか。この村を救ってみぬか」
「救う…。」
六蔵は初めて声を発した。
「そうじゃとも、入定(にゅうじょう)して即身仏となって衆生を救うのじゃ」
「入定、即身仏」
六蔵は呟いてみた。聞き覚えのある言葉だ。
入定とは禅では精神を統一して煩悩を去り、無我の境地に入ることだが
高僧が死ぬことの意味もある。死んでそのまま仏になることを即身仏という。
「わが偉大なる師、法雲上人の話は何度もおまえに聞かせたはず。今一度聞かせよう。
法雲様はある村の名主の子じゃった。
金持ちの子として生まれたことを羞(は)じておられた。
飢饉が起こるたびに身代を擲(なげう)って人々を助けようとされた。
しかしそんなことではとても人々を救い切れぬと気がついて仏門に入られた。
そして、様々な苦しみの元である肉体からの解脱を図られた。
目の病が流行れば自らの目をえぐって病の終焉を仏に祈られた」
六蔵は身動きできないままにその先をだんだん思い出しながら
法海和尚のだみ声を聞いている。
「法雲様はなかなかの男前じゃったからある時、
松原の山水桜の遊女に思いを寄せられて困っておられた。
行く先々にその遊女が現れる。法話の途中でも嬌声をあげる。
わしら弟子仲間は面白がって囃(はや)し立てたりした。
日頃、高邁な仏説を説いておられるのでどうなさるかと興味津々じゃった。
あまり遊女につきまとわれてどうしょうもなくなった時、
ついに、陽物を切り取ってお与えになってしもうた」
六蔵はこの男根を切り取った話を小坊主時代に聞いて
幼い心が畏れでいっぱいになった。
とても自分にはできない、とただひたすら
その法雲という僧に畏敬の念を持ったものだった。
「あの時は驚いた。いくら肉体を否定してもそこまでできるとは思わなんだ。
色即是空とはわしらも唱えはしたが、今でもようわからん。
その師が浅間山の噴火や冷害で起きた天明の大飢饉の折りに
民衆の救済を願って即身仏となられたのじゃ。
この寺の離れに開かずのお堂があったことを憶えておるか。
あそこに法雲上人の即身仏、則ち、ミイラが安置されているのじゃ」
「ミイラ…」
「そうじゃ、食を断ち、肉体が腐らぬように漆を呑み、生きながら仏となる。
それが即身仏」
「ま、まさか、首切りの方があっさり死ねてましじゃないか」
「どうせ死ぬのなら同じではないか、六っ、即身仏となれ」
「そんなものなりとうないわ。おれはとうの昔にこの寺と縁が切れた。
坊主の自分がなればいい」
「うむ、しかし、わしにはせねばならぬことがある。毎日飢えて、
あるいは流行り病で、その上おまえような野盗に殺されて、
あの世に赴く衆生の供養に忙しい」
「わしゃ知らん。どうせ、明日は首と胴が離れるんじゃ。
勝手にみんな苦しめばいいわ」
「同じ死ぬにしても死に方というものがあろうが。
村人にはわしから話しておく。明日から始める。覚悟しておけ」
母屋には村人の総代として与平の死んだ後に名主となった弥助が待っていた。
「待たせたな、弥助さん。六蔵は渡すわけにゆかんようになった。
あいつめ改心して即身仏になると申しました」
「しかし、ご住職、あの男はただの盗人ではございません。
笠原の赤鬼と呼ばれたお尋ね者です。この村の恥でございます。
近郷の村の衆は夜も眠れず暮らしておりました。
やっと野良仕事に精が出せると喜んでいるのです。
昔のお弟子さんだからと言って決して逃したり
匿(かくま)ったりして命を助けようとしないでください。
明日はお役人が来るのですから渡す首がないと困るのです」
「馬鹿者!なんということを言う。わしをなんと思うておる。
万が一にもそのようなことがあれば、わしの首を鋸でひいて役人に渡してくれ」
弥助は法海の大喝に縮みあがった。
「それでは、今から穴掘りのうまい衆をみつくろって頼んできます。
明日は早そうなのでこの辺で」
弥助は決断すると行動が早かった。ぺこりと頭を下げて出ていった。
心の底ではこの和尚が失敗して困るのを見たいとも思った。
******************************************************
六蔵は縄で縛られて転がされたままあたりを見回した。
本尊の大日如来が見おろしている。
「お久しぶりです。如来様、六は人でなしになって帰ってきました。
罪滅ぼしに即身仏にならなければならないそうです。
法雲様が入定されたとき、人々は救われたのでしょうか、
飢饉は終わったのでしょうか、流行病(はやりやまい)は焉(や)んだのでしょうか。
わたくしには信じられません。
わたくしのような者が入定したところで人ひとり救われるとは思えません」
六蔵は返事をしない仏像にいらだって身じろぎした。
すると、どうしたことか、あれほどきつかった縄がゆるんでいる。
激しく身をよじると思いがけなく簡単にほどけてきた。
からんだ縄をふりほどいて仁王立ちになった。
「く、く、く、く」
腹の底から笑いがこみ上げてきた。
(つづく)