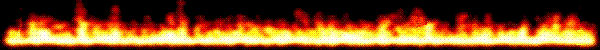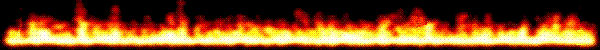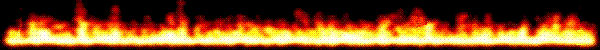
 『炎で書いた物語』最終章6
『炎で書いた物語』最終章6
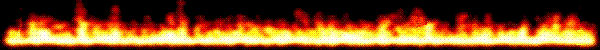
<しあわせ未来形4>( DO PEOPLE DO)
それでは、最終連である第****連に入る。
普通、作者は、章分けするとき、数字を使ったり、上、下、などを使用してなるべくわかりやすくする。
それぞれの連の番号に数字でなくなぜこの読みにくい*のマークを使用してあるのだろうか。
これでは、ある連を指定するとき、*連のどことか**連のどこそことなって非常にわかり辛い。
章と呼べば良いのか連が良いのかも不明だがここではぼくは一応詩編として連と呼んでいる。
****
>>
>> この数を見よ、と片目の男は言った。
>> 愚かな数を見よと。
ここでいよいよ最も難解と思われる数霊が提出された。
数霊につてはこの物語の始まりの辺りでとりあげたので重複する部分が多くなるがふたたび触れなければならない。復習させようという意図があるようだ。
****というマークで第四連を始めているのは偶然ではない。
なんの手がかりもなく唐突に、この数を見よ、というのは見るべき数が見あたらないのでまるで言いがかりのように思えるが、手がかりは****にある。
この****という数を見よ、と言っているのである。
つまり、四という数を問題にしているのである。
ここで主語「片目の男」がだれであるのかの特定をしてしまおう。
アイパッチで一時勇名を馳せたイスラエル軍のダヤン将軍や伊達政宗や柳生十兵衛、隻眼隻手の怪人、丹下左膳のように現実界や虚構の人間を想定すれば良いのか、
それとも、なにかの比喩として使用されているのだろうか。
「この数」を子の数と考えれば、だれかの親である方と思える。
この物語の推移から推し量って、片目の男性でだれかの親であることが当てはまる方は、
黄泉平坂から帰った伊奘諾尊(いざなぎのみこと)である。
かれは伊奘冉尊の力を借りることなく黄泉国の汚穢(けがれ)の禊ぎの間に、左目から天照大神を生んだ。
ということはそのときその時点では伊奘諾尊は右目だけの隻眼であることになる。
伊奘諾尊が片目の状態で生んだ子、天照大神の数を御代(見よ)で三四=七と言っている。
そしてその数を愚かな数であるという。
見よ、に注意を向けるためにたった二行に二度も「見よ」を使っている。
その右眼だけで見て判断しているのだ。右眼は右岸でありこの世のことである。
そして、それはのちに生まれる「月読命」の眼に映っている世界である。
「月読命」の眼を通して見た天照大神の数が御代(見よ)で三四というのはおかしい。
それでは、「月読命」の世界となんの変わりもない。
月読は三四三である。
「光の黙示録」からこの見よ(三四)に関する部分を引用する。
>>
>>読みは四と三
>>月は三
>>月読みは三と四と三 日読みも 三と四と三であった
>>(今は そうでは無いという意味)
月読みは三と四と三であるのに、「日読み」でも三と四と三でしかない。
日である天照大神が月と同じ挌であるということになる。
つまり、この「天照大神」は真の「天照太神」ではなかったと思われる。
真の「天照太神」の大にはチョンがあり、「天照大神」は物質太陽で三の数霊の日で女性だった。
伊奘諾尊おひとりで左目から生んだ子、天照大神は実は物質としての日であって
その数を三四=七といって愚かな数と言っているのである。
この数****、愚数=偶数である四が特に愚かであるらしい。
なんらかの失敗があったようだ。四ではいけなかったと思われる。
月と日の中心に来る数字が四では困るのだ。
物質太陽(三)と月(三)に囲まれると、どちらから見ても七になって開けない。
そこで次の行でその修正案が語られる。
>> 彼の指からは、さらさらとこぼれ落ちるものがあった。
彼の指をシと読んで彼の死(四)からは新、更、とこぼれ落ちるものがあったと読む。
伊奘諾尊は兵庫県津名郡一宮町で死んでから、伊奘諾尊神宮を幽宮(かくれのみや)にして
淡路国一の宮、多賀大明神となった。
死(四)から新なる更生をするためには一が必要なのだ。
一の宮(霊家)とは霊数、一がかくれている宮のことである。
それが一の宮の意味である。四に一が加わって五となる。それが再生の数なのだ。
伊奘諾尊はその失敗を補うために一の数を持って一の宮で時を待っておられるのである。
三四三の中心にその一が入るとき、蓮華の花が八(パッ)と開くのである。
そのとき世界は三五三で中心に真の天照太神を抱くことになる。どこから見ても八の世界である。
三
三五三
三
>>
>>太陽はエール 三、四、三
>>月はミューア 三、四、三
>>エールとミューアで 二〇
>>最高神が 一〇
>>一〇を分けた二〇であれば均衡状態
>>(今はそうでは無いらしい)~~~~~~~~
>>今 現在の数については 教えて貰っていません
「最高神が 一〇」というのに「一〇を分けた二〇であれば」という。
一〇を分けるとき、われわれは五と五に分ける。マーケットで一〇円玉を分けてくれと言っても二〇円にしてくれることはない。鋏で切られても困るだけだ。
すなわち、前にも述べたが、一〇は十のことではないのだ。
(今はそうでは無いらしい)ということは、その「一〇を分けた二〇であれば均衡状態」であった時代があったのである。
その時代、最高神一〇は、一〇を分けて二〇であった。
それは古代エジプトで、太陽神RA(ラー)を逆読みして(エール)と、
月神AUM(オーム)を(ミューア)と呼んだころであろう。
それが古代の呪法であった。
「エールとミューアで 二〇」というのは二十ではなく二つの○ということである。
最高神一〇は自身を二〇に分けた。
しかし、それでは均衡状態で回転ができないので
三四五の世界とされた。
それがこれまでの御代(三四)と死後(四五)の世界の成り立ちであった。
真の天照太神の数(五)はこれまで隔り世を照らしていたが時至って中心に位置されることになる。
>> 梟は夜を嫌い、
梟は黄泉(四三)の使者として登場してくる。
かれも夜(四)を嫌っている。
>> 野鼠は藁を敷かずに眠った。
野鼠(八祖)とは八の祖で八の開く時代の祖となる方である。
耶蘇とみるとキリストの登場となる。
それで「藁を敷かずに眠った。」
という厩で生まれたキリストを暗示させる表現をとっている。
加賀山弘氏の「秘密結社の記号学」(人文書院)によると
「キリスト教における数値の象徴主義者においては、八という数字はイエスの復活の象徴としてきた。
それは八日にイエスが復活し、イエスの名前はギリシャ文字の数値変換では
十、八、二百、七十、四百、二百となり、その合計は八八八となるためであった」とある。
『10Ι(イオタ)+8Η(エータ)+200Τ(タウ)+70Π(ピー)(パイ)+400Φ(フィー)(ファイ)+200Τ(タウ)=888』
上のようなギリシャ文字を使った式で表される。
ノアの方舟伝説において八人の人間が助かったことなどでも八を復活の象徴と考えた。
このようにキリスト教でも八は復活の数であると見られる。
しかし、「藁を敷かずに眠った。」の意味がまだ不明である。
なんのことやらわからない。
藁を四数(かず)に根六った。などと考えても届きそうで届かない。
こうなれば伝家の宝刀、逆読み法を試してみよう。
やそはわらをしかずにねむつた
YASOHAWARAOSIKAZUNINEMUTA
逆読みして「集め似ぬ咲き祖あらわほさい」となって近づいたようだが「ほさい」がおかしいので
野鼠をノネズミと読んで
NONEZUMIHAWARAOSIKAZUNINEMUTAとすると、
集め似ぬ咲き祖あらわひむゼノン
あつめにぬさきそあらわひむゼノン
ゼノンは古代ギリシャの哲学者で「ゼノンの逆説」で有名である。
「飛ぶ矢は止まっている」とか「足の速いアキレスも亀に追いつけない」と主張した。
これでも、意味がつかめない。どうもゼノンはこの預言に無関係のようである。
もうすこし煮詰めてみよう。いつも、ここらへんであきらめて惜しいところで逃げられる。
「あつめにぬさきそあらわひむせのん」を
『集め似ぬ先祖露秘む世音』としてみる。
こうみるとやっと姿が見えてきた。
世音は観世音でタテの日、
わかりやすく意訳すれば
「似てもいないわれわれの先祖をこれまで集めてきたが、秘められてきた本当の先祖である
音(タテの日)は露にされる。」
やっと意味が通じた。
ここで始めの行の「片目の男」に戻って「男」の意味を考えよう。
「男」は田の回転をする力で伊奘諾尊にふさわしい。
伊奘諾尊は子産みのためにおひとりで回転をされたのだろう。
オトコと読めばそれが音子であることがわかる。
つまり、「音」タテ棒の日の子である。伊奘諾尊ご自身がタテの|を口に秘めた音であった。
それがここまでにぼんやり見えてきたこの連の意図である。
これから第四連の中枢部に入るのだが長大になることが予想されるので
ここから先は項を改めて目先をを変えて解くことにしてひとまずここでこの項を閉じよう。
最終章(その6おわり)