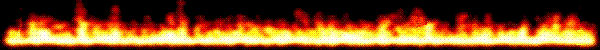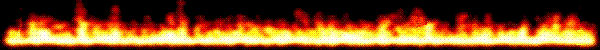<We all need love.>(その5の上)
渡米後、しばらくプライベート・スクールに通ったぼくはとても
毎月の授業料が払い続けられないので公立の学校に転校した。
転校後しばらくして新しい学校に馴れた頃、魅力的な日本人女性が入学してきた。
それが妻である。
その学校は毎週金曜日には趣向を凝らしてみんなで楽しむことになっていた。
ある週の金曜エンタメントに先生に頼まれて、
中古の安物ギターをかき鳴らしてスリー・ドッグ・ナイトの「シャンバラ」を 歌った。
みんな意味がよくわからないようだった。
歌っている本人がわからないのだからしかたない。意味はわからなくとも好きな歌だった。
歌詞を掲げると著作権法に抵触するので割愛するが
「シャンバラでは光はどんなふうに輝くのか」というような内容だった。
はなさんが言及された光の黙示録の一節にそのなつかしのシャンバラが含まれていたので引用する。
>>「アガルタに行くのに肉体はいらない。途上に肉体が必要なだけだ。
>>アガルタに入る前に、肉体を脱いでいく。ある場所でそれを実行
>>するのだ。その場所は、少しずつ位置を変えながらあなた方の世
>>界とシャンバラとの入り口を形成している。」
>> +----------------------------------------------+
>> | U |
>> | \成 的 矢/鏑 |
>> | 月(円) \ / (円)日 |
>> | \ / |
>> | (雲の絵) 音 × 弦 (雲の絵) |
>> | / \ |
>> | / 須 \ |
>> | 花瓶 /波 礼\ |
>> | |
>> | 弓 (| 退 悪 |) 玉 |
>> | 神 (| 久 大 魔 |) 置 |
>> | 楽 (| 胎 金 |) 宮 |
>> | (| 日(田) |) |
>> | |
>> +----------------------------------------------+
再度この玉置神社のお札の図を掲げておく。
アガルタの出てくる詩編があるのでこの図にあてはめてみよう。
>>
>><27>
>>
>> アガルタの宮使い
>> 釜石の山 中程よりきたりて
>> 笛の音にて其方 呼ぶ
>>
>> この言葉 縦糸とせよ
>>
>> 十字の形に組んだ足
>> 未だ覚めやらぬ街々の四隅に
>> うずくまる 者々
>>
>> この言葉 横糸とせよ
アガルタの宮とはこの玉置宮のような気がする。
大
胎 金
日(田)
この回転曼陀羅の大は人であり胎蔵界、金剛界を巡り、ついに上がる田(アガルタ)に入る。
そこから第三の道が始まる。
アガルタの宮使いとはやはりこの図に関係の深いスサノオさんなのだろう。
釜石は大と金が重なった部分。矢の組み合わせと金でもそう見える。
笛は竹の由であるが日に縦棒が加わった「由」の字に注目したい。
日が縦棒のヒ(音)を加えて田になることを知らせる笛なのだろう。
スサノオが笛の音でアガルタ=上がる田を知らせる。
そこまでが縦糸とされる。
十字の形に組んだ足は矢が葦でできているからか。
未だ覚めやらぬのはまだ明けていないから
「うずくまる」は疼く○で疼いている○とはなんだろう。
街は行く土、土。動いている土と考えられる。
者は土ノ日のことである。それは地球のこと。
疼く○も行く土も土の日もすべて地球を指していた。
それが横糸とされる。
この縦糸と横糸が組み合わされて新たな時代の繊維が織りあげられようとしている。
スサノオの吹く笛の音が縦糸で地球が横糸。
織物に音は欠かせない。「織」として糸(意図)を音が司る。
そしてついには肉体の執着をを脱いでアガルタ=上がる田へと入って行く。
双六の上がりのようにこのステージを上がった人類は次のステージ、シャンバラへと進む。
(この項、長くなるので以下をその5の下としてを分載する)