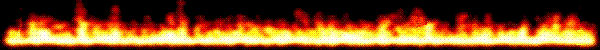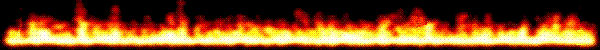<We all need love.>(その2)
>> +--------------------------------------------−+
>>下手 | U端 幕 |上手
>> | 雁又\成 的 矢/鏑 |
>> | 月(円) \ / (円)日|
>> | \ / |
>> | (雲の絵) 音 × 弦 (雲の絵) |
>> | / \ 土 |
>> | 松 / 須 \ 師 |
>> | 明 花瓶 /波 礼 部 |
>> | |
>> | 弓 (| 退 悪 |) 玉 |
>> | 神 (| 久 大 魔 |) 置 |
>> | 楽 (| 胎 金 赤 |) 宮 |
>> | (| 日 龍|) |
>> | |
>> +----------------------------------------------+
(客席)
上図にあてはめて読み解きつつある光の黙示録の前回に続く部分を見ていただこう。
>> 吾が宮つ城を踏みにじる者に災いあれ
>>吾は龍宮の長、不二の高嶺に立つもの
>>龍宮の変を知らぬ 其方では無かろう
>>冥府の従僕を吾が従僕にするために
>>其方のするべき事を教える
ここで語られていることは龍宮の長であり、富士の高嶺に立つ偉大な存在が
自分の領域を踏みにじる無法者に対して怒りわれわれに冥府の従僕、悪魔をこちらがわの
味方にひきいれる方法を教えようとしているらしい。
その具体的な方法がつぎに語られている。
>>ホホデミの炎の剣を ハジベの所へ
>>持って行け
>>青龍の吐く息で精錬せよ
>>冥府の従僕を眠らせ 赤龍を呼べ
>>赤龍の吐く息を従僕の裡に呼び込み
>>炎最大となった時に ホホデミ青龍剣を
>>振り下ろし 炎の根元から切り分けよ
>>其方達 吾が従僕よ
>>吾が報せをよくよく胸に留め
>>ゆめゆめ忘れること無かれ
このままではなにがなんだかわからないから一行ずつ見ていこう。
>> ホホデミの炎の剣を ハジベの所へ
>>持って行け
まずホホデミでつまづいてしまうがこの図の中に限定して考える。
前回見たユカタンはU化端かもしれない。雁股は獣や鳥の足を切るためにU字形になっていて
刃が付いている、その部分を剣と呼ぶ。ホホは火火で重なると炎、ミは月と考えて
ここではホホデミの炎の剣は三日月のような月の形をした雁股と仮定する。
この図には他には剣らしきものが見あたらない。
雁又=仮の又=亦を土師部の所へ持っていくと
亦と土師部の土が重なり「赤」になる。
>>青龍の吐く息で精錬せよ
青龍の吐息=十息で精錬すれば赤は十と一体になって「十赤」となる。
こんな字はないのでまだ意味がわからない。
>>冥府の従僕を眠らせ 赤龍を呼べ
>>赤龍の吐く息を従僕の裡に呼び込み
冥府の従僕、悪魔の裡に赤龍の吐く赤い吐息=十息を呼び込めば
「悪十赤魔」と長ったらしくになる。
>>炎最大となった時に ホホデミ青龍剣を
>>振り下ろし 炎の根元から切り分けよ
炎が最大になった状態、「悪十赤痲鬼」を精錬後のホホデミ青龍剣、
すなわち「十赤」を振り下ろし根本から切り分けると
すべての十の部分と赤がはずれ落ち
最後に残ったものは「心」だけであった。
この長い作業を経て結晶したものは
悪の脚の「心」と鬼のチョン付き田を支える「心」だった。
>>其方達 吾が従僕よ
>>吾が報せをよくよく胸に留め
>>ゆめゆめ忘れること無かれ
吾が報らせの中身は「心」だった。
心を胸に留めると「思」う、になる。
ゆめゆめ、決して忘れてくれるなということであるが、それは
忘れる、すなわち、心を亡くす。そのようなことのないようにという戒めであった。
それが冥府の従僕、悪魔をもわれらの従僕とすることのできる方法なのだから。
切り分けた十赤と心、カミのセキシン、神の誠の心ということのようである。
この結論に達するまでずいぶんまわりくどい道をたどったが
結局、悪も魔も心を土台にしている。冥府の従僕となるも神の従僕となるも
人々の心次第なのである。
これはそのことに気づかせようとするパズルのような詩であった。
(つづく)