●


 森
森 と湖
と湖 の讃歌
の讃歌
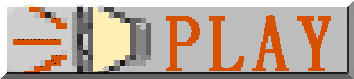
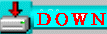



ルークはギターの祖先にあたる楽器、リュートの名手である。
かれの爪弾くリュートは近所の娘たちの評判だった。
祭りが近づくと、毎晩人気のない森で稽古に励んだ。
ある夜、背中でハミングを聞いて少しムッとした。
練習しているところを見られるのは嫌いなのだ。
「誰っ、邪魔するなよ」
「ごめんなさい、わたし、テイ。あなたがルークね。
あんまり、お月様がきれいだからついフラフラと散歩に来ちゃった」
「若い娘が夜中にウロウロしている危ないよ」
「大丈夫、こう見えても強いのよ。いざとなれば男のひとりやふたり」
「もし、ぼくが襲ったら…。」
ルークはこの地方の槍のチャンピオンだった。
チェスのルークのように一直線に進むのでルークと呼ばれている。
「あなたは、そんんなことしないと信じてるもの。
それより、今の曲もう一度弾いてわたしに歌わせて」
ルークは黙ってリュートを弾きはじめた。
テイの澄んだ声が澱んだ夜の空気を震わせる。
なんて美しい声なんだ…。ルークは乙女の横顔をまじまじと見た。
どこか見覚えがある。幼い頃の面影を残して成長した近くの乙女だから
見知っているのだろうか、と思った。
テイは微笑みながら歌い終わる。
ルークはリュートを置いて衝動的に娘を抱き寄せた。
テイは予期していたのか、もがきながら男の手からのがれて
何も言わず足早に立ち去った。
つぎの夜は月もなく暗かった。ルークは一晩中リュートを弾いた。
テイを心待ちにしていたが、ついに姿をあらわさなかった。
そのつぎの夜は月が明るかった。
背後から聞こえるハミングに思わず振り向くとあの微笑みがあった。
「あの曲弾いてわたしに歌わせて」
ルークはうなづいた。
乙女の歌声が木々の隙間を縫ってゆく。
森の精霊たちも息を殺して聞きほれている。
それから毎晩テイはやってきた。この地方の民謡はほとんど稽古し尽くした。
「今度の祭りは楽しみだね。この郷にこんなすばらしい歌姫がいたなんて、
みんなびっくりするよ」
「お願いがあるの。わたしたちの命を育んでくれるこの森や湖に捧げる歌を作
ってほしいの」
「ぼくたちは森や湖を汚すばかりで
感謝したこともないものね。」
「隣の郷ともうまくいっていないし、この森や湖も悲しがっていると思うの。
この地方を平和な郷に戻すために歌を歌いたいの」
そのころ、隣の郷と漁業権や領域をめぐってあちこちで小競り合いが起こっ
ていた。いさかいの種はどこにでもころがっていた。
ささいなことでも一触即発の状況にあった。
ルークは昼間、馬や槍の稽古を怠らず暇を見つけて歌作りに励んだ。
そんななかでも人々が心待ちにしていた祭りの日がやってきた。
ルークとテイは舞台にのぼった。
テイはまず、この地方の民謡を歌った。
天才的な歌姫の誕生をだれもが感じた。
鳴り止まぬ拍手の中でテイは次ぎの曲を紹介した。
「つぎの歌は『森と湖の讃歌』といいます。
まだ未完成なんですけれど歌います。
この歌で郷が平和になって繁栄すれば本当に完成したことになります」
テイが歌い出すと会場がどよめいた。
人々は手を取り合って
この地方の自然に感謝する心で結ばれた。
みんなの力でこの歌を完成しようね…。
そのとき、会場の後ろでざわめきが起こる。
隣郷の兵士たちがなだれこんできたのだ。
人々は泣き叫び逃げまどう。
昔から祭りの間はお互い攻撃しないということになっていた。
ルークは槍をとって馬に乗った。
あちらでもこちらでも戦いが始まっている。
ルークは果敢に襲いかかり勇猛に働いた。
卑怯者めら…。
愛馬を駆って矢のように突き進む。
郷の境を突破して逃げる敵兵をなぎ倒す。
いつもならそこでやめるところだが、はやりすぎていた。
深追いしすぎて敵の真っ直中にいた。
振り向くと退路が完全にふさがれている。
逃げ道を求めて回ろうとしたとき、
敵が放った矢が愛馬の尻に刺さった。
棒立ちになった馬からもんどりうって落ちた。
グギッと首の骨の折れる鈍い音を感じた。
「ごめんね、テイ、『森と湖の歌』を完成できなくなってしまった。
いつかまた、どこかできみと出会えたら…。」
薄れる意識の中でルークはテイによびかけた。
敵兵は若者の目尻に涙が一筋こぼれているのをみつけた。
「なんだ、こいつ泣いてやがる、臆病者め。
てこずらせやがって」
兵たちは哄笑を残して立ち去っていった。
終わり





 と湖
と湖 の讃歌
の讃歌



