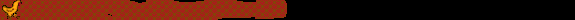わたしはアパートを早く出よう、と思っていた。家賃が高いので貯金があまり長くもちそうもなかったのだ。
そんなとき、上のクラスの生徒がふたりやってきて一緒にホームステイ先求むの新聞広告を出そうか、と誘う。そのうちのひとりが 上田好久だった。
わたしたちはどんな文面が良いか考えながら ロサンジェルス・タイムス社に向かった。社に着いて広告部で説明すると文面を簡単に作成してくれる。費用は三人で出し合って翌日の紙面を待った。
連絡先を学校の電話番号にしておいたのでロサンジェルス・タイムスの広告に反応して翌日から学校の事務所に電話が入るようになった。そのたびに三人で面接にでかけた。ビバリーヒルズの大邸宅だったりダウンタウンの普通の家庭だったりいろいろだったがみんな断られた。なかなか決まらないものだと感じたが、そのうちにハリウッドヒルをかなり登ったハリウッドサインのそばあたりの大きな家に面接に行った。「この家のペンキを塗ってほしいの」と奥さんがいう。三人のうちだれがいいか、と訊くとわたしを選んだ。それでその家のペンキ塗りとしてホームステイすることになった。
とにかくこれで家賃から解放される、この国にすこしは長く滞在できそうになった、と思った。
***** ********
授業で自己紹介の時自分の星座を言わなければならないのでアクエリアス と言った。蟹座はキャンサーと教わった。ホームステイの話題が出た時、ユダヤの家庭だけには入りたくないという人が多かった。ユダヤの家に入るとこき使われるぞ、という。ユダヤについての知識はそういえばシェークスピアの「ベニスの商人」の強欲な商人がユダヤ人だったな、とか「アンネの日記」に代表される第二次世界大戦中のホロコーストの被害者ということぐらいだった。入りたくないといってもだれがユダヤ人かという見分け方も知らないし、わたしは漠然とそんなものかと思っていた。
毎朝、6時頃起きて、裏のハリウッドサインを見上げると、たまになにか飛行機のようでそうでないような飛行体が上昇していった。この裏あたりがUFOの基地になっているのかも…、と思ったりした。黒かった壁に白いペンキを塗っていると奥さんがハズバンドはキャンサーという。初めは授業で習った蟹座のことかと思った。しかしそれは癌のことだった。かかっているのではなくUCLAの癌科の医師だったのだ。大変な職業だと思った。
可愛い息子がふたりいて食事中、叫び声が絶えなかった。夜、わたしが疲れて椅子にもたれて眠っていると足に小便してゆく。それに気づいた奥さんが「オー・マイ・ロード」と嘆声をあげる。いつもなにかあると「オー・マイ・ロード」だった。テレビや街では「オー・マイ・ゴッド」を聞くことが多かったので不思議だった。訊いてみると「うちはジューイッシュなので、『オー・マイ・ロード』というのよ」という。それでこの家はユダヤ人家庭なのだ、と初めてわかった。
医師夫婦は仲が良くて子供達との喧噪の夕食後、わたしにギターの弾き語りを所望する。最近の曲がいいか、と訊くと「ラヴ・ミー・テンダー」がいい、という。それでギターを抱えて歌い始めると、抱き合って踊りだした。西洋人の年はわかりにくいがまだ30代前半で恋人気分が残っているらしかった。そしてある日奥さんが日本の歌も聴かせてよ、という。それで日本のカラオケのレコードをバックにしてわたしが歌ったカセットテープをかけた。ふーん、これが日本の音楽、とやはりあまり反応はかんばしくなかったがカスバの女 に大きく反応した。「これはジューイッシュ・メロデイよ。聴いたことがあるわ、どうして日本にユダヤの歌があるの」と訊く。わたしは返事のしようがなかった。ただなぜか最後の「外人部隊の白い服」という歌詞で映像が浮かんできて胸が迫る思いがするので選んで歌ってみただけだったから。この曲のもつ切ないともエキゾチックともやるせないともなんとも表現のしにくい雰囲気はジューイッシュ・メロデイだからなのか、と思った。
わたしはアメリカのクリスマスに興味があった。盛大に祝うのだろうと期待していた。家庭では七面鳥を焼いて食べるのだろう。日本とどんなふうに違うのだろうと。
12月に入ってしばらくすると学校でクリスマスパーテイがあった。
アルコール類はなかったがダンスしたりパンチを飲んだり談笑していると先生たちがみんな若いことに気づいた。20代後半から30代の女性が主で校長と副校長ぐらいが50代だった。パーテイの最後あたりにしつらえられたにわかステージに登ってギターを抱えて、リクエストに応えて当時のヒット曲を歌った。一番受けたのはヒットチャート1位を走るロッド・スチュワートの「トゥナイツ・ザ・ナイト」 だった。若い先生達も一緒に手拍子して首をふりコーラスする。うれしかった。文化はすべての壁を破る。パーテイが終わると女の先生達が一斉にやってくる。「あなたレベルCクラスの生徒でしょ。どうしてレベルCなの。Aでしょ」ワイワイがやがやうるさく質問してくる。歌は発音をコピーして何度も稽古するのでほとんどそのまま歌える。その歌手が南部訛ならその発音のまま歌う。ビートルズも自分たちで喋るときは英国リヴァプール訛だったが歌うときは米国南部訛が多かった。先生達に答えようとすると言葉がうまく繋がらず、やっぱりレベルCであることが判明した。めでたしめでたし。
そろそろ世間の家庭でクリスマスツリーが飾られだしたことが報じられだした。みんな、この季節になるとマーケットの庭に並べられる樅の木を買って帰って居間に飾るらしい。もうすぐわたしのホームステイ家庭でも樅の木を買ってクリスマスツリーを飾るのかとアメリカの家庭で経験する初めてのクリスマスを楽しみにしていた。子供がふたりいるのでデコレーションに凝るだろうし手伝おうと思って待っていた。しかしいつになってもそれらしい気配はない。「うちはジューイッシュなので、クリスマスは祝わないの。」とある日奥さんが言う。それでユダヤ家庭にはクリスマスが無関係なことを知った。「そうかといって、わたしたちの世代はユダヤ教の儀式もしないの」そういえばこの家には宗教的なものがなにもないことに気づいた。人種としてはユダヤ人であっても無宗教で暮らしているらしかった。実際に一緒に生活すると映画や本でみるユダヤのイメージでは測れないものがあった。こうしてこの年のわたしの米国生活初のクリスマスは期待に反したものになった。
「でも、そのかわり、よく働いてくれるからプレゼントを買ってあげるわ」と車で丘を下りてZODYSと称する雑貨マーケットに連れて行ってくれた。そのとき白いコットンパンツとイーグルスのアルバム「ホテル・カリフォルニア」を買って帰った。コットンパンツの裾上げを自分でして縫っていると「ミシンがないからどうしようかと思ってたの、そうなの自分でできるの」と奥さんが驚く。日本で小学校の家庭科の時間に針と糸の使い方ぐらいは習ったから当たり前だった。アメリカではミシンがなければ裾も上げられないらしいことにこちらのほうが驚いた。このとき、手に入れた「ホテル・カリフォルニア」 はこの日から計り知れない夢を与え続けてくれた。ドン・フェルダーがマリブの海に沈む夕陽を眺めながら紡ぎだした永久の回転を思わせるあのギター進行。理解できそうでできない歌詞、それらがわたしをとりこにした。わたしは文字通り「ホテル・カリフォルニア」の囚われ人となろうとしていたのだ。
アルバム「ホテル・カリフォルニア」からは先行シングルとしてまず「ニュー・キッド・イン・タウン」 がリリースされてヒットしていた。「ニュー・キッド・イン・タウン」はフミオのことね、とこの曲は奥さんのお気に入りだった。翌年にはヒットチャートのトップグループに入るほどになった。ところが第二弾シングルとして「ホテル・カリフォルニア」がラジオから流れ始めると奥さんの表情が曇るようになった。聴くのをいやがるのだ。なぜかわからなかった。「わたしは、こんなところ来たくなかった。ニュー・ヨークは良かった。窓から外を見てるだけでも毎日なにかがあって楽しかった。ここにはなにもない」と嘆き出す。こんなに素敵な所、という歌詞の内容に反発を感じているらしい。そういえば近所づき合いはないし、ゴミを外に出すときにも人に見られるのを嫌がる。「カリフォルニアは嫌いなの。ニュー・ヨークに帰りたい」と訴える。それを毎日ベッドルームで夫に言い続けているらしかった。「今度、ワシントンにハズバンドが仕事見つけに行くの。ここ以外で暮らしたいから頼んだの。あなたに壁を塗ってもらうのはこの家をきれいにして高く売るためなのよ。親に援助してもらって25万ドルで買ったの」。意外だった。カリフォルニアが嫌いとは…。そのうちに本当に夫は車でワシントンに仕事探しに?かけていった。病院巡りをしているらしくなかなか帰ってこない。この家には長くいられないらしいと感じた。
「昨夜、ワシントンから電話があったの。ハズバンドが働く病院がみつかったのよ。あなたも一緒に来てくれる」と奥さんが訊く。家族でもないのについて行くのはおかしい。学校で友達に相談する。すると一緒にホームスティ先探ししたひとり、エイブが日本人学生数人で一軒家をシェアしているので来い、という。なんだか一家に悪い気がしたがワシントンに行きたくないので医師が帰って来る前に慌ただしく奥さんに別れを告げた。壁はまだ全部は塗り終えてはいなかったがかなりきれいになっていた。すこしは値段が上がるかもしれなかった。
*********** *********
逃げるようにしてハリウッドヒルをあとにして落ち着いたのは西南区の黒人が多い地区だった。夜、5人ほどの同居仲間に挨拶してステレオをセットしてラジオをつけた。するとラジオの音をかき消すようにヘリコプターの音が聞こえる。みんなで飛び出して探照灯が照らし人が集まっている方へ走る。すると発砲音がして通りの黒人が倒れた。パトカーが集まってきて警官が倒れた黒人の死を確かめていた。夜の捜査線のひとつの結末らしかった。
路上に溢れた血液を見て、このあたりでは夜飛び出すと危ないことに気づいた。
翌日には路上の血液はもうきれいに洗い浄められて事件を思わせるものはなくなっていた。噂では昨夜の事件は麻薬がらみのトラブルの後始末のようだった。その地域は西南区クレンショー地区10thアベニューなのでなんでも音楽に関連づけるわたしの脳裏にベンチヤーズの「十番街の殺人」 (Slaughter On Tenth Avenue)が繰り返し鳴り響いた。しかし、幸いその後の米国生活で人が殺されるのを目にすることはなくこの国は危険という感覚はうすれていった。
それよりもそのときのわたしの課題は如何に所持金を長持ちさせるかということだった。住むところはみんなで家賃食費を出し合う形で最低限で済むようになった。しかし、とにかく今の学校は私立校なので学費が問題だった。早晩貯金が尽きてしまう。そこで政府が援助して授業料がタダの学校があると聞いて転校することにした。それはアダルト・スクールで大人を対象にしてENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL) PROGRAM、すなわち英語を第二国語とする人を育成することが目的のプログラムを実行していた。それまで面識もなく住ませてもらう挨拶もしていなかった10thアベニューの家の日系人大家さんに訳を説明して保証人のサインを無理矢理のようにもらってそのアダルト・スクールを訪ねた。そこは学校とはいうもののそれらしくなく家具屋の二階だった。授業料はまったくのタダではなく半年に50セントだという。一応払っているという形をとっているのだ。それならわたしにぴったりだった。クラスメイトは前の学校とは大違いでイラン人が多かった。米国政府の対外政策は毎年変わりその年はイラン人留学生を大量に受け入れていたのだ。パーレビ政権下で苦しむイラン民衆をそんなふうに応援していたのだ。かれらは自国で王を批判すると危ないがここでは毎日政治の話題に熱中していた。授業中も休み時間も男子女子を問わずとにかくうるさかった。
クラスの構成はイラン50パーセント、ラテン系30パーセント、日本10パーセント、その他10パーセントといったところだった。雑多な人種が混じり合いそれぞれの目的のために英語を学んでいた。一大勢力のイラン人が常にワイワイ発言し日本人はおとなしかった。ラテン系は冗談好きでわたしに「ジョソイ・ロコ」と言えという。わたしがそういうと大喜びした。それは「ぼくは頭がおかしい」という意味だった。当たってはいるけれど言え、といっておいて言ったからといって、バカにして囃すのは子供みたいだった。それぞれに民族性が違うことを知ることができて良かった。あるとき隣の席のアルゼンチン娘が「男のものは日本語でどう言うの」と訊く。わたしはそんなことを訊かれると思っていなかったので虚を衝かれて外国人にどう教えたらいいのか、あなたもきっと迷うように少し迷ってノートにchin chinと書いた。すると、そうチンチン、わたしの国では女のほうはこういうのとラテン語らしいスペルをノートに書く。わたしは確かめるためにその言葉を発音してみた。すると突然態度が変わり「声にだして読まないで」と眉をしかめて怒りだした。自分が先に訊いておいて勝手に怒るな、と思ったがまわりのラテン系の人には意味がわかるから戒めたのだろう。おかげで一瞬見たその言葉は覚えることができなかった。残念なようなそうでもないような気がした。かの女はのちに米国永住権を得るために日系人ではなく中国系アメリカ人と結婚したからあの日本語はかの女の語彙に入らず忘れ去られてしまったことだろう。残念なようなそうでもないような、どうでもいいような…。
日本人は大学に入るための英語力アップが目的の人が多く正しい英語を話そうとする。議論も考えてから喋るので口が重かった。他の民族は文法的に合っていようが合っていまいがお構いなしにとにかく喋りまくるので上達が早かった。イラン人たちはみんな大声で意見を述べ合うのだがその中にも思慮深げな人物はいて、みんなが騒いだあと静かに締めのようなことをいう。そして他民族の代表のようにわたしにも意見を訊く。わたしは部外者としての意見を述べた。かれらはチェスが好きで昼休みも休み時間も集まって楽しんでいた。チャンピオンらしいヒゲの男が脇を通ろうとするわたしを見とがめてチェスをしようと誘う。他民族代表としてわたしをチェスという知的競技に誘っているようだった。わたしは日本将棋は好きだったがチェスはあまりやったことがなくどうせ歯が立たないから断った。勝負するのなら勝てないにしてもいい勝負ぐらいにはしたかったから。
そしてある日「ボビー・フィッシャーのチェス必勝法」という本を図書館で借りて帰った。何日か真剣に勉強してチェックメイト(詰み)のテクニックや基本定跡を覚えて、昼休みに集まって騒いでいるチェス好きのそばに素知らぬ顔で近づいた。やはり一通り対戦相手に勝ったクラスのチャンピオンが手持ち無沙汰になってわたしを誘うので仕方なさそうに受けて立った。油断していたらしく局面は覚えた定跡通り進み、チャンピオンは不思議そうに自分のキングを倒した。かれはボビー・フィッシャーに負けたようなものだった。申し訳ないような気がした。いくら強くても自信過剰で定跡にはまるといけない。
やがてアダルトスクールの主要メンバーであったイランからの留学生達はいつのまにか姿を消し気が付くと本国イランでは親米強硬路線パーレビ政権が倒された。イランイスラム革命と呼ばれる革命が勃発したのだ。あの留学生達も新政権樹立に働いたのだろう。残念なのは革命後振り子の反動のようにあまりにもナショナリズムが強くなりすぎたことだった。あの思慮深げな人物のような指導者が中枢になってコントロールすることができなかったのかもしれない。
* * * *
そろそろ、車を購入しようと思った。この街ロサンジェルスは世界で一番広いことで有名なので仕事をするには車が必要だった。日本語新聞「羅府新報」の売買欄で「中古車売りたし」を見て車に詳しい友達と何カ所か廻った。見かけは良くとも走るうちにハンドルがちょっとずれたりするものは事故車のようでやめて最終的にポンティアックGTOを450ドルで買った。なぜならロニーとディトナスのGTO という曲が好きだったから。それは以前サーフィンミュージックとともに流行したホット・ロッド音楽で、米国のバイク界を席巻した リトル・ホンダと並ぶ名曲だった。残念ながらリトル・ホンダのほうは社名が入っているのでNHKではあまり流れない。わたしには車の善し悪しは判断できないのでそんなことで決めたのだ。とにかくこれで車が手に入った。スピードは出さずよたよた、あるいはヨロヨロという感じで毎日稽古し慣れるとやっと学校まで走った。
経済的にいよいよ逼迫して早くなんとかしなくてはならない。そんなとき、10thアベニューの学生寮のようになった家に転がり込んできた女子学生が夜、日本人街(リトル・トーキョー)の日本食レストランでアルバイトを始めてその店のピアノバーでエンターティナーを探しているという。早速、GTOにギター、譜面その他を積んでその店に向かった。店を探して夜のリトル・トーキョーをグルグル廻っていると不審車両と思われたらしくLAPD(ロサンジェルス警察)のオートバイに停められた。わけを言うとその店の場所を教えてくれた。店のオーナーは女性ピアニストを探していたのだがギターの弾き語りをしてみせると仕方ないと思われたのか採用された。夜9時から朝2時まで演奏すること。それが米国での初めての仕事だった。女性ピアニストが好みのオーナーの意向には反していたがバーテンダーやスシ職人など従業員には評判が良かった。
********* *********
「今度入った日本娘きれいだぞ、フミオ、」イスラエル軍のパイロットだった生徒がある日、ニヤニヤする。その娘はわたしの後ろの席に座った。それが一生の伴侶との邂逅の瞬間だった。今もそのとき覗いた瞳の輝きを鮮やかに覚えている。いろいろ学校のことや英語のことを尋ねてくる。わたしは隣に移動する。妹夫婦の結婚式に喚ばれて式に出席したのだがせっかくアメリカに来たのだからしばらく滞在して英語を覚えたいから入学したという。授業が終わるとサンタモニカのアパートへ車で送った。サンタモニカ方面の道はヘビー・トラフィックで慣れていないので運転初心者のわたしにはとてもこわかった。
それから現在までかの女は毎日、わたしとともに過ごすことになった。 昼休みには車で食べに出た。一番頻繁に通ったのは学校に近かったラ・ブレア・タールピッツ にある美術館博物館群のひとつLAカウンテイ・ミュージアム のカフェテラスだった。その頃まだアメリカには余裕があってそれらの施設の入場料はタダだった。画学生たちが名作の前で何時間も模倣している。世界最高級の美術品をじっくりゆっくり堪能できた。そのカフェテラスのサラダは一人前をふたりで食べても食べきれないほどの量があった。
********************* *************
やがて当然のようにマリポサ通りのアパートを借りてふたりで暮らし始めた。
そのうち、ふたりが結婚することは学校中の衆知の事実のようになった。ある日、クラスにふたりで帰ってくると突然先生も生徒もみんなでサプライズ!コングラチュレーションズと叫ぶ。サプライズパーティが始まったのだ。贈り物やカンパの金を渡され、なにか歌えと所望される。それで「♪恋が計算通りにできるなら、こんな女(男)に惚れたりしなかった。あれこれ迷ってそろばん 弾き、それでもやっぱりこいつに決めた〜」と日本語だったけれどふたりで自作の歌を披露した。今にして思えばあのイスラエル軍パイロット出身の男はキューピッドだった。名前はもう忘れてしまったが今頃どこでどうしていることだろう。わたしたちの名前も忘れてしまっただろうか。そう、縁結びの神は海外出張して多くの糸の中からふたりを選り分けて結んでくれたのだ…。
**********************
わたしの妻となることになったこの女性は日本で教習所に通って自動車運転免許証を取得していた。運転免許はこの国では身分証明書として頻繁に必要になるから、わたしごときが人に教えるのはおこがましいけれど米国の運転免許取得のためにと、日本とのルールの違いの認識や安全確認の重要性を力説してしばらく稽古につき合った。すると78点で合格した。運転もうまいといわれたという。良かったことは良かったけれどなんだか気が抜けた。当たり前だけどわたしの場合ほど心配することはなかったらしい。
************
わたしたちは結婚式場を探した。どこがいいかさっぱりわからなかった。日本人の牧師さんがやっている教会に頼んでみようかと相談してセントメアリーという教会を訪ねた。しかし信徒さんでなければだめです、と期待は虚しくあっさり断られた。それでイエローページを調べて日本の芸能人がよく結婚しにやってくるという ガラスの教会を見つけた。そこは寄付金(ドーネーション)を納めれば良いということだった。電話すると土日の寄付金が一番高くて金曜日が割安だったので1978年2月17日(金)に決めた。結婚記念日はそんな経済的理由で決まった。
そのランチョー・パロス・ヴァーデス地区にある太平洋に面した丘の上のスエーデンボルグ系の教会、Wayfarer’s(徒歩旅行者)Chapelは帝国ホテルの建築家、フランク・ロイド・ライト(1869-1959) がなんと日光東照宮大猷院(たいゆういん)を模して設計したものだった。
そのころ、GTOのラジエターから水が漏れてオーバーヒートすることが多くなってしばらく走るとすぐ停まるようになったのでフォード社のピントーという中古コンパクトカーを手に入れた。
1978年1月の小雨降る日、授業が終わってオリンピック通りを東に走ってウェスターン通りとの交差点の信号が黄色になって左にターンしているとき、信号が変わる前に渡ろうとスピードをあげて突っ込んできた車と衝突した。フォード・ピントーは数回回転して止まった。わたしたちは少しの間気絶していた。やはり左折が問題だったようだ。
バス停で待っていた人々が一斉に集まってきて介抱してくれる。それはほとんどがアフリカ系アメリカ人(黒人)だった。身動きできずボーとしたまま、ただ親切な人たちだと感謝した。救急車がやってきて運び込まれたUSCジェネラルホスピタルで診察を受ける。わたしたちは額をフロントガラスにぶつけ、わたしは額に入った割れたガラスの破片をとってもらい、妊娠4ヶ月目だった妻は目の上が膨れたが、他に異常がなく安心した。
翌日、ジャンク・ヤードに車を見に行くと完全にクラッシュして使いものにならないことがわかった。トランクの中にあったギターその他の仕事道具を調べるとだれかがすでに持っていってしまっていた。日本語の譜面まで盗らなくても、と思った。妻は身につけていた財布をとられていた。車の中を何度探しても見つからなかった。だれかが介抱しているふりをしてとったらしい。そのころのわたしたちは気絶している間も気を抜けない、ということをまだ知らなかった。
とりあえず仕事に車がいるのでわたしは急いでドイツの大衆車メーカー、オペル社のアストラ・クーペの中古車を購入した。結局その車をこまめに修理したり手入れして日本に帰国するまで使用することになった。わたしは夜は弾き語り、昼は学校という生活を続けた。そのころふたりで居住したマリポサ通りのアパートにはそれほど長くは住まなかったのだがそれでもいろいろなことがあった。隣の若い黒人が麻薬でおかしくなって窓から飛び降りようと自殺しかけて取り押さえられたり、煙がどこからか流れてきて火事騒ぎで避難したり、駐車場に駐車しておいたGTOのイグニションキーホールのシリンダー部分が工具で外されていたり、そのあたりでは人が見ていないとなるとなんとか車を盗もうとするらしかった。
*********************
そうこうするうちに結婚式が近づく。ブーケ・トスのためのブーケを注文して当日取りに行く約束した。事故でぶつけて腫れた妻の目の上のたんこぶは日を追ってだんだん小さくなって血が下りてきて目のまわりを黒くしてきた。濃いシャドウのようになった。
当日は金曜ということで先生も生徒もほとんど出席できない。家族も親戚もいない、ただ数人の友達だけの前で執り行うシンプルな結婚式だった。意味がわからない神父さんの言葉をオウム返しに唱える。神父さんは苦笑いしながら祝福する。それでも神の前で永久を誓い正式に結ばれたのだ。なにもないただふたりの出発だった。
あの日、わたしたちに降り注いだカリフォルニア・サンシャイン は今もふたりの心に輝き続けている。序章、了。