阿曼陀羅の風
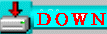
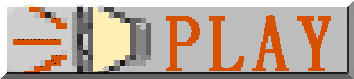

(自由への脱出)
なんの前触れもなく夏が来た。
湿った空気が体全体にべとつくようにまとわりついている。
都会の闇はいつもどこからか光を誘い込み白っぽい。
そのおかげでこんな夜更けにひとりでさまよっていてもあまり恐怖心は起こらない。
このあたりは、この時間には人影が途絶えてしまう。昼間の喧噪が嘘のようだ。
わたしはあいつのえらそうな態度を思い出して唇を噛む。
「いい加減にしてよ。何様のつもり、
わたしをあんな牢獄のようなところに永遠に閉じこめておけると思ってるの」
熱い汗が怒りとともに吹き出てくる。
「きみは自分の幸せに気づいていないんだ。こうして毎日、
なんの不自由もなく食べてゆけるのだから。
外に出てやっていけるはずないさ…」
喧嘩のたびにあいつはそう言って高をくくっていた。
わたしは悔しかったけど最後には我慢ししてきた。
やっぱり不安だったのだ。でも今は違う。精神的にずいぶん成長したと自分でも思う。
あいつはいつまでもそれに気づかないでいた。いや、気づこうとしなかった。
--自立、自立…。
と念仏のようにくり返しながら歩いていると
胸の奥でしこりになっていた不安が少しずつ溶けてゆく。
これからは自分の力で生きていくのだ。きっと立派に自立してみせる。
今日は自分の意志で始めての一歩を出した記念の日だ。
興奮が治まってくると背後で足音がしているように思えた。
ビルの谷間に響く足音が自分のものだけではないような気がする。
足を停めるとその足音も停まる。
歩き出すとまたその足音も歩き出す。振り向こうか、振り向くまいかと迷う。
--気のせいかしら、きっとそうね、そうに決まってる。
自分に言い聞かせながら背中に神経を集中する。
空が曇ってきたのか、街灯のないせいか、
さっきまで明るかった闇が今は黒く濃く垂れ込めている。
脇の下を冷たい汗が流れる。都会の闇をバカにしていたつけがまわってきた。
額の汗はぬるくなって頬を伝わる。
忘れていたはずの恐怖心が背筋をつかむ。わたしはできるだけ足を速めた。
昼間に行動する動物の本能的な恐怖心なのだろう。
その闇から一刻も早く逃れたかった。わずかでも光がさす場所に出たかった。
思い切ってただ闇雲に駆け出した。
かなり走って立ち止まった。振り向いてみた。だれもいない。
闇を透かしても動くものの気配はなかった。
--はじめからだれもついて来なかったんだ、きっとそうだ。
荒い息をつきながら顔を手でおおった。汗まみれだ。おもわず自分自身を笑ってしま
う。
--こんなことで自立だなんておこがましいのかも知れないわ。
考えてみればあいつの言うとおりかもしれない。
これまでなんの不安もなく暮らしてこれたのはあいつのおかげだったのだ。
あんな粗末な場所でも一応住むことはできた。
こんなつまらない畏れを感じることもなかった。
これからは雨露をしのぐ所も自分で探さなければいけない。
身が引き締まる思いがする。
わたしはまた歩き始めた。
さっきの足音がまたついてくるような気がする。
気にしないことにする。他のことを考えよう。
--狭いながらも楽しいわが家か、案外あの生活がわたしに似合ってたのかしら
あいつもあれでやさしいところもあったし、たのもしかった。
でも、そんなふうに考えちゃいけない。
せっかく一大決心をして飛び出してきたんだもの。
もっとしっかりしなくちゃ。
それにしてもこの町並みは暗かった。いつになっても明るい場所に出ない。
足音がイヤに大きく響く。きっと日光の鳴き龍のように足音がコンクリートにはね返っ
て
響きやすい地帯なのだ。
角を右に曲がったとき、目の隅にだれかの影が映った。ドキンッとする。
心臓がうなりをあげて博ちだした。
やっぱりだれかつけてきている。間違いない。
さっき走ったとき一度は逃げ切れた。
なんというしつこさだ。もっと走っておけば良かった。
-どうしょう、どうしょう、だれか助けて…。
足がすくんでしまった。振り向こうとしても 振り向けない。
このままでは襲われる。こんな目に遭うのなら出てこなければ良かった。
身を守るものなどなにひとつ持っていない。なんとかしなければ…。
--そうだ、もしかしたら相手もこわがっているかもしれない。
こっちから奇襲してひるんだ隙に逃げ出せばいい。
振り向いて。大声あげて顔に頭突きして逃げよう。畏れてばかりいられない。
これからは自分で自分を守るのだ。助かる方法はそれしかない。
決心がつくとすーっと腹が据わった。背中で近づく相手の息づかいをはかる。
一気に振り向いて叫び声をあげた。
目の前に相手の顔があった。わたしに抱きつく寸前だった。
ひしゃげた鼻、耳まで裂けた分厚い唇、全身を包む剛毛。
野生動物のもつすえたような臭い、オランウータン…。
圧倒的な力を秘めた長い腕がわたしを抱き寄せる。
わたしは抗(あらが)うことなく身をまかせる。
激しく狂おしい時間がわたしの上を通り過ぎていった…。
 突然、あたりが明るくなった。目の眩(くら)むライトが浴びせられた。
突然、あたりが明るくなった。目の眩(くら)むライトが浴びせられた。
サイレンが聴覚も奪う。
わたしたちは手に手を取って逃げる。
しかし、後ろはデッド・エンドだった。
かれはわたしをかばって雄々しく立ちはだかる。
追手の目にはかれの体は数倍に見えたことだろう。
わたしは恐怖にひるんだ男たちの表情が白く変わるのを盗み見る。
ライフル銃が向けられる。わたしは身を縮めてかれの陰に隠れる。
かれは鼓膜も破れるほどの威嚇の雄叫びをあげた。
脅えた隊員たちの銃から轟音を立てて銃弾が何十発となく発射された。
わたしをかばう類人猿の体が小刻みに震えながら崩れ落ちた。
--麒(き)ーっ…。
わたしはかれの魂の抜け殻にとりすがって泣き叫んだ。
まるで破れた縫いぐるみみたいだった。
あちこちから流れ出た血を一生懸命なめる。
ゆすってもゆすっても自分で動く気配はなかった。
ムラムラと怒りが胸に満ちた。
かつて経験したことのないほどの怒りが堰を切って溢れた。
わたしは立ち上がり、銃口に向かって吠えた。
隊員たちの顔から血の気がひいて蒼ざめた。
わたしは許すことはできなかった。かれらに襲いかかった。
つぎの瞬間、かれらの銃は再び火を噴いた。
わたしは何度もジャンプしながら麒の上に折り重なって斃(たお)れた。
夜明けの街角で若者たちが騒いでいる。
「なにがあったの」
「ああ、オランウータンの捕獲劇だってさ。射殺されたらしいぜ、二匹とも。
なんでも雌が動物園の檻を破って逃げだしたんだって。
雄もそれを追って逃げたそうだよ。
追いつめられて刃向かってきたから仕方なしに撃っちゃったんだって。
でもそのとき、見たこともないような怪物に変身したそうなんだ。
集団幻視(マーヤ)かな、笑っちゃうよ。
でも、殺すことないよな。俺だってあんな檻のなかで一生暮らしたくないもん。
そりゃ、逃げるさ」
オランウータンの体を抜け出たわたしたちは他人(ひと)事のように聞いている。
「麒(き)、このつぎ生まれ変わったら何になりたい?」
「きみと会えるんだったら何でもいいよ、麟(りん)…」
キラキラした光がふたりを包む。
その光に導かれてわたしたちはふんわり地上を離れた。
(了)



 突然、あたりが明るくなった。目の眩(くら)むライトが浴びせられた。
突然、あたりが明るくなった。目の眩(くら)むライトが浴びせられた。

